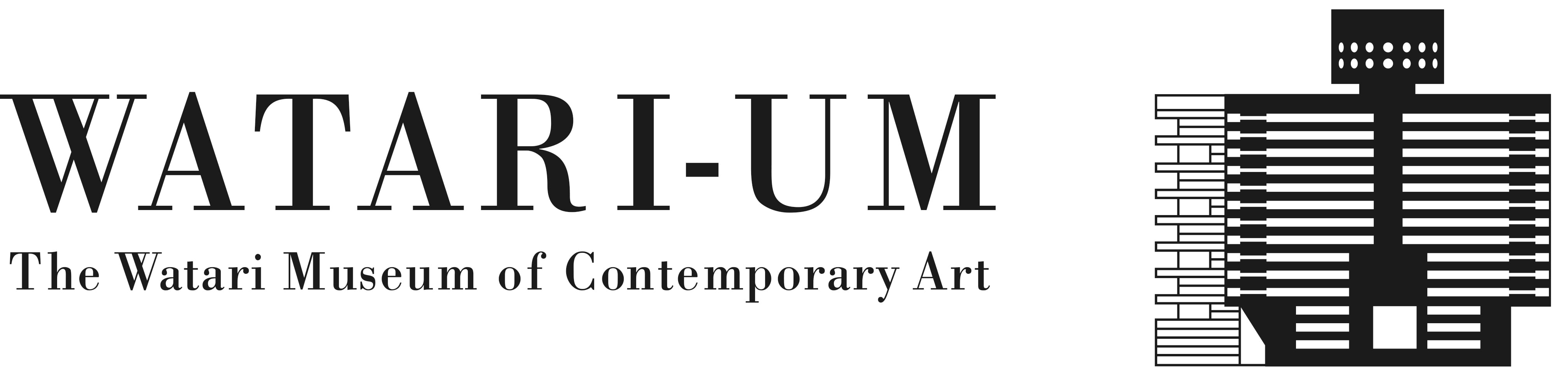山田寅次郎オスマン倶楽部2025
高官たちの会食光景 1727年 トプカプ宮殿博物館所蔵
参加者募集
全6回:2025年10月〜2026年2月
金曜19:00-20:30
会場:ワタリウム美術館
講師:津本英利、鈴木董、川本智史、ヤマンラール水野美奈子、今井 宏平、和多利月子
オスマン時代に生まれた華やかな文化・芸術は、時代を超え、
現在にその魅力を届けています。
オスマン倶楽部2025は、古代アナトリア文明から現在のトルコ共和国まで、各分野の〈泰斗〉をお迎えし学びます。
ワタリウム美術館 メンバーシップ会員の方には割引がございます。
ワタリウム美術館1F受付でもお申込いただけます。
◆スケジュール
① 古代:「古代アナトリアに製鉄の起源を探る」
10月31日(金) 講師:津本英利(古代オリエント博物館 研究部長)
「人類最古の鉄の使用はヒッタイト帝国に遡る」と長らく言われてきました。実際には鉄利用の歴史はヒッタイト以前に遡り、大村幸弘率いる中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所の調査団は、人類最古の製鉄の起源を求めて、長らくトルコ中央部のカマン・カレホユックで発掘を続けて来ました。「空から降った金属」と人類との出会い、ヒッタイト帝国における鉄利用の実態とは?紀元前1200年頃に鉄器時代はどのように始まり、鉄器の使用はどのように広まったのか?など、人類と鉄の古代史についてお話しします。
② 文化:「トルコ駐箚日本大使館がイスタンブルにあった時代の駐土日本大使たち -そのプロフィール-」
11月21日(金) 講師:鈴木董(東京大学名誉教授・トルコ歴史学協会名誉会員)
オスマン帝国時代には、日土間の交流はあり、国交交渉も行われたが、国交開始には至らなかった。日土の国交が開かれたのは、オスマン帝国が終焉し、トルコ共和国の独立後の、1924年に日本がローザンヌ条約の批准書を寄託した時であった。早速、在外公館を開くこととなり、1925年にトルコ駐箚日本大使館が開設された。ただ、その場所は、トルコ共和国の新首都アンカラではなく、かつてのオスマン帝国の帝都イスタンブルだった。というのは、オスマン帝国時代、各国はみな、公館をイスタンブルに置いていた。そして、新首都アンカラは建設中で、海からのアクセスもなかった。そこで、各国の公館は皆、イスタンブルに残っていたので、日本もそれにならったのである。この講演では、日本大使館がイスタンブルにあった1925年から1937年までに赴任した大使たちのプロフィールを紹介したい。
③ 建築:「オスマン帝国の民家」
12月5日(金) 講師:川本智史(東京外国語大学総合国際学研究院 准教授)
現在トルコ共和国を訪れると、各地で歴史的な民家を目にすることができます。中でも世界遺産に登録されたサフランボルは観光地としても有名です。しかしオスマン帝国の長い歴史や地域性に目を向けると、サフランボルだけではない多様で豊かな民家の伝統が浮かび上がってきます。アルバニアからシリア、さらにはエジプトに至るまで、かつてオスマン帝国が支配した地域には独自性と共通点をもつ民家が現存しています。またトルコ国内だけをみても、18世紀の民家と20世紀初頭の民家は大きく異なるものであり、地域性も強く感じられるのです。その多様性とおおまかな変遷をご紹介したいと思います。
④ 美術:「オスマン美術と食文化」
1月23日(金)2026年 講師:ヤマンラール水野美奈子(トルコ美術史家、元龍谷大学教授)
トルコ民族は中央アジアからイランを通りアナトリア半島・バルカン半島に移動しながら、多くの地域や民族の芸術や文化を吸収しました。オスマン帝国では国家の繁栄と共にそれらが一挙に開花したとも言えます。食文化もこうした環境の中で育まれ、美術と言う造形のなかにおいても食文化は一つのテーマとして盛んに表現されました。オスマン時代の美術工芸品や絵画から読み取れる’礼節としての食’、’祝祭における食’、’市井における食’、’家庭での食’などについてお話しします。
⑤ 現代:「現代トルコの政治・外交・経済(公正発展党期を中心に)」
2月6日(金)講師:今井 宏平(アジア経済研究所 地域研究センター 中東・南アジア研究グループ 副主任調査研究員)
トルコでは、2002年11月の総選挙でレジェップ・タイイプ・エルドアン率いる公正発展党が勝利し、与党になってから四半世紀が過ぎようとしている。エルドアンは首相、そして大統領として、建国の父アタテュルクが志向した方向性とは異なる形で、国際社会におけるトルコの存在感を高めてきた。本講演では、公正発展党期の約四半世紀を中心に、トルコの政治・外交・経済について概観し、トルコが今後、どのような道を歩んでいこうとしているのか、検討する。
⑥ 外伝:「新月・山田寅次郎と紅雲・伊東忠太」
2月27日(金) 講師:和多利月子(ワタリウム美術館)
1904年コンスタンチノプルで出会った2人は、年齢も近く〈文化〉という共通点から互いを尊敬し、旅で見たものや日々感じたことを絵葉書にしたため送っていました。2人は両国の文化と芸術をどのように感じていたのでしょうか。
現在も残っているおよそ180枚の絵葉書から当時の様子を紐解いていきます。
◆講師紹介
津本英利:1970年岡山市生まれ。筑波大学やマールブルク大学(ドイツ)で考古学を学ぶ。学生時代よりトルコ(カマン・カレホユック、クシャックル、カヤルプナル)、シリア、イスラエルでの発掘調査に従事。著書に『ヒッタイト帝国 「鉄の王国」の実像』(PHP新書)、『古代オリエントガイドブック』(共編著:新泉社)などがある。
鈴木董:1947年藤沢市生まれ。東京大学法学部卒、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、法学博士。1972-75年イスタンブール大学文学部に留学。1983年東京大学東洋文化研究所助教授、1991年同教授、2012年定年退職し東京大学名誉教授となり現在に至る。オスマン帝国史を専門とし、比較史・比較文化に関心をもつ。
川本智史:工学博士(東京大学大学院、2013年)。著書に「オスマン朝宮殿の建築史」ほか。
ヤマンラール水野美奈子:1944年東京生まれ。慶應義塾大学文学研究科修士課程終了、イスタンブル大学にて文学博士号取得。
今井 宏平:Ph.D. (International Relations). 博士(政治学)。著書に『トルコ100年の歴史を歩く: 首都アンカラでたどる近代国家への道』平凡社、2023、『戦略的ヘッジングと安全保障の追求:2010年代以降のトルコ外交』有信堂、2023、『エルドアン時代のトルコ:内政と外交の政治力学』(岩坂将充との共著)岩波書店、2023、『トルコ現代史』中央公論新社、2023、編著に『クルド問題』岩波書店、2022、『教養としての中東政治』ミネルヴァ書房、2022などがある。現代トルコの政治と外交に関して、国際関係論および比較政治の枠組みから検証を行なっている。
参加費:全6回 12,000円/ワタリウム美術館 サポート会員:8,000円/アートパス会員:10,000円
※原則、お申込のキャンセルは、お受けできません。あらかじめご了承ください。
※講師の都合により、日程が変更されることもございます。