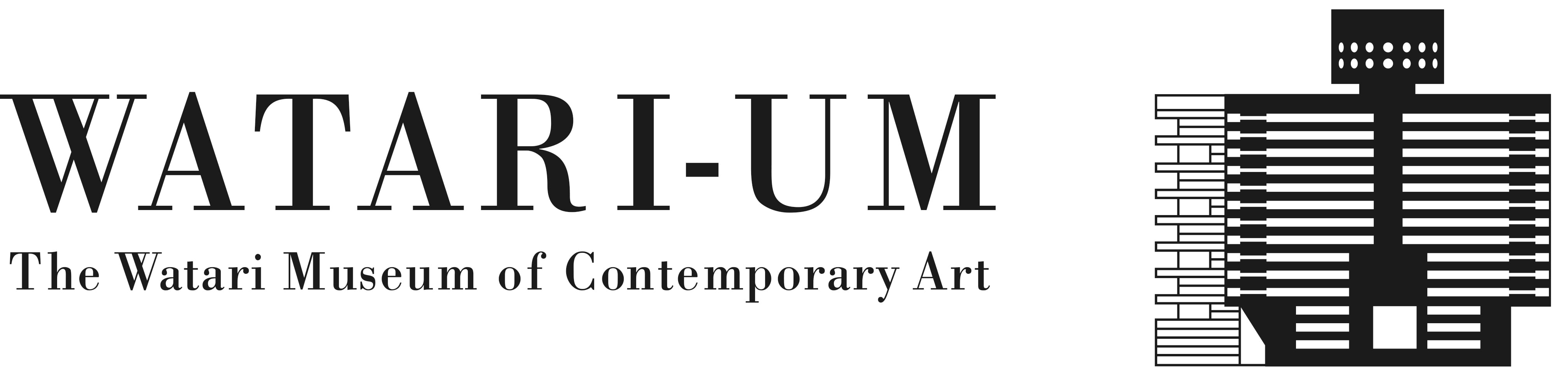レクチャーシリーズ+見学会
新・和室学2025
建築家が挑んだ「和室」の世界
和室は、日本人にとって当たり前の存在でありながら、失われつつある危機にあります。改めて和室の意味や成り立ちを知り、特徴を多角的に読み解くことで、その魅力を再発見したいーそんな思いからこの連続講座を企画しました。世界で日本にしかない「和室」という空間を、各分野の専門家が深く語ります。
2025年度は、建築家が挑んだ「和室」の世界がテーマです。日本の住宅は、近代の洋風住宅の導入によって大きく変化しました。その中で建築家たちは、自らの考えで「和室」の設計に取り組み、「伝統」と「革新」、「様式」と「個性」の狭間で戦いを挑みました。その多様な手法と展開を、建築家ごとに掘り下げます。
2025年度 会員募集
会期:2025年4月から10月
レクチャー4回+1日見学会1回
講師:
上西明(建築家、現代・和室の会 常任幹事)
藤岡洋保(東京工業大学 名誉教授)
内田青蔵(神奈川大学建築学部 特任教授、現代・和室の会 会長)
小沢朝江(東海大学建築都市学部 教授、現代・和室の会 副会長)
主催・会場:ワタリウム美術館
協力:現代・和室の会
◆スケジュール
見学会を除き、各回とも 金曜19:00-21:00
2025年4月18日(金)
第1回「谷口吉郎」上西明
今から約50年前の1971年、「現代の数寄屋」(伊藤ていじ+二川幸夫、淡交社)という本が刊行されました。そこでは、村野藤吾、吉田五十八、堀口捨己、谷口吉郎ら、近代建築家たちの設計による「和室」が紹介されています。谷口吉郎(1904-1979)は、「清らかな意匠」をデザインの目標にかかげ、モダニズムの原点にある気品、清涼な表現を、数々の作品のなかに結実させました。谷口吉郎の設計による游心亭は、迎賓館赤坂離宮に建てられ、その写しが金沢建築館につくられました。それら二つの游心亭など、谷口吉郎の手になる「和室」を通して、「和室」の豊かさ、これからの可能性について考えていきたいと思います。
2025年5月23日(金)
第2回「堀口捨己」藤岡洋保
堀口捨己(1895-1984)は和風建築の大家といわれますが、それは「日本回帰」したからではなく、茶室が、茶の湯の点前という機能に対応し、非相称の空間構成を持つことから、西洋にはるかに先んじてモダニズムを実践した建築で、その特徴をとり入れて成立した数寄屋風書院こそが日本の和室の到達点と考えていたことがもとになっています。それは「モダニズムのフィルターを通した伝統理解」で、茶室に新たな意味を見いだしつつ、名席や千利休研究の成果をもとに、八勝館の「みゆきの間」や「残月の間」「さくらの間」「きくの間」のような傑作を生み出しました。この講演では、堀口特有の和室の形成過程を資料や実作をもとに紹介します。
2025年6月7日(土)
見学会「鎌倉宝庵(旧関口邸茶室)」(山口文象設計)小沢朝江
山口文象(1902-1978)は、逓信省の製図工からスタートし、日本初の建築運動団体「分離派建築会」に参加、モダニズムを牽引する存在として活躍した建築家です。その一方、祖父・父とも大工の家に生まれ育ち、伝統的な和風建築にも精通しました。「鎌倉宝庵」は、朝日新聞等で活躍したジャーナリスト・関口泰の自邸に営まれた「常安軒」と「夢窓庵」の2棟の茶室で、山口がドイツのW・グロピウスの事務所から帰国直後に設計しました。名茶室の写しに、グロピウス直伝のモダニズムを加えた独自の空間を特別に見学します。
2025年9月26日(金)
第3回「吉田五十八」内田青蔵
吉田五十八(1894-1974)は近代数寄屋を生み出したことで知られています。それは、近代という新しい時代にふさわしい”和室”の提案ということができます。吉田は、”和室”を江戸期に完成した過去のものとは捉えずに、時代とともに変化し、成長するものと考えていたのです。その考えを明確にし、公表したのは昭和10年(1935)の「近代数寄屋住宅と明朗性」であり、一気呵成に作品づくりを展開したのです。そこで、今回は晩年に手掛けた旧岸信介邸を事例とし、吉田の考案した新時代の”和室”の特徴を整理し、今後の新時代にふさわしい新たな”和室”の追及の一助としたいと思います。
2025年10月24日(金)
第4回「村野藤吾」小沢朝江
村野藤吾(1891-1984)は、古典様式の最末期に建築活動を開始、個性的な素材感と芳醇な細部意匠で、画一的なモダニズムと反する独自のスタイルを築きました。その和風建築は、作家・井上靖により、小堀遠州になぞらえて「きれい寂び」と賞されました。武者小路千家で茶道を学び、如庵や残月亭など著名な茶室を写しながら、伝統の直写ではない独自の空間を設計しました。「写し」という手法を通して、村野の豊かな和室のバリエーションを読み解きます。
◆講師紹介
上西明(うえにし・あきら) 建築家、現代・和室の会 常任幹事
1959年生まれ。東京大学大学院修士課程修了。槇総合計画事務所を経て、上西建築都市設計事務所を設立。主な作品に、奈良県医師会センター、岩尾整形外科病院、大田区うめのき園分場など。共著に『ヒルサイドテラス白書』(住まいの図書館出版局,1995)、『都市のあこがれ』(鹿島出版会,2009)、『劇場空間への誘い』(鹿島出版会,2010)。(『和室学』第7章「モダニズム建築の和室」執筆)
藤岡洋保(ふじおか・ひろやす)東京工業大学 名誉教授
1949年広島市生まれ。東京工業大学博士課程建築学専攻修了、工学博士。明治大学工学部助手などを経て、1984年東京工業大学工学部助教授、1996年同教授、2015年定年退職。2003年東京工業大学教育賞、2011年日本建築学会賞(論文)。2013年「建築と社会」賞受賞。 2021年海上保安庁長官表彰。近著に『SD選書 堀口捨己の世界』(鹿島出版会、2024)、他に『表現者 堀口捨己─総合芸術の探求』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築 日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)、『堀口捨己建築論集』(編著、岩波書店、2023)など。
内田青蔵(うちだ・せいぞう)神奈川大学建築学部 特任教授、現代・和室の会 会長
東京工業大学大学院理工学研究科博士課程満期退学。工学博士。東京工業大学附属工業高校、文化女子大学、埼玉大学を経て、神奈川大学教授。2022年3月に退職し現職。
著書に『あめりか屋商品住宅』(住まいの図書館出版局,1987)、『日本の近代住宅』(鹿島出版会,1992)、『新版図説 近代日本住宅史』(共著、鹿島出版会、2008)、『住まいの建築史 近代日本編』(創元社、2023)ほか多数。(『和室学』第6章「明治維新以後の和室」執筆)
小沢朝江(おざわ・あさえ)東海大学建築都市学部 教授、現代・和室の会 副会長
1963年生まれ。神奈川大学大学院修士課程修了。博士(工学)。著書に『日本住居史』(共著、吉川弘文館、2006)、『明治の皇室建築―国家が求めた〈和風〉像』 (吉川弘文館、2008)、『住まいの生命力 清水組住宅の100年』(共著、柏書房、2020)など。(『和室学』第3章「近世和室の豊饒な世界」執筆)
「現代・和室の会」
「和室文化」を総合的に把握し、その固有の価値や多義的意味を解き明かしながら、次世代への継承と無形文化財としての国際認知を目指す団体です。和室と関わる多方面の研究者や行政、設計者、職人・生産者等で構成し、セミナー・見学会等の活動を行っています。出版として、『和室学』(共著、平凡社、2020)、『和室礼賛』(共著、晶文社、2022)。